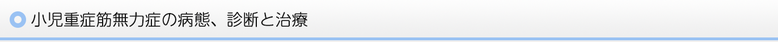
- 小児重症筋無力症は珍しい病気か
- 自己免疫疾患としての小児重症筋無力症
- 胸腺について
- 家族歴がある場合
- MGを持つ母親から生まれた赤ちゃん
- MGの診断
- 治療
市立宇和島病院 小児科
林 正俊
小児期に発症する重症筋無力症(MG)は、小児期の難病の一つとして今まで研究が進んできました。神経難病の代表疾患であるMGの研究は、わが国では厚生労働省の免疫性神経疾患研究班が先頭を切って進めてきて、その診断、治療の進歩は目を見張るものがあります。
病態の解明も進んで、自己抗体が原因となる自己免疫疾患であり、その病態理解によって治療も合理的な選択が可能な時代になってきております。
以下、現在のMGという疾患について確立されてきたところをまとめてみます。
小児重症筋無力症は珍しい病気か
小児科医が一般診療の中で子供の重症筋無力症(MG)を診る機会はめったにあるものではありません。恐らく小児科開業医の先生が普段の診療で出会うのは1人あるかどうかでしょうし、基幹病院ですら、人口規模にもよりますが、数名から十数名といったところだろうと思います。
厚生労働省が2006年に疫学調査を行いました。その結果、本症患者数は成人も含めて約1万人に1人、そのうち小児の発症頻度は1.6%と報告されました。図示したグラフからもわかる通り(図1)、わが国では5歳未満に大きなピークがあります。これは日本だけの特徴ではなく、中国、香港、韓国でも同じ発症パターンを示しており、東アジアの民族の特徴と考えられています。小児期の筋無力症は欧米では大変珍しく、その病態の研究などはそう簡単にできるものではありません。その点では、我が国でこそ病態研究を進めていきたいと考えています。

(図1)
自己免疫疾患としての小児重症筋無力症
(ア)重症筋無力症の病態発見の時代
重症筋無力症が自己免疫疾患であるという発見は、1973年Jim Patrickがシビレエイの発電器官からアセチルコリン受容体〈AChR〉を抽出し、それを家兎に免疫することによって、家兎に人と同じ病態を作ることに成功したという報告で明らかになりました。
その後1976年にLindstromによって、患者血清中にAChR 抗体が存在し、その高さが重症度と相関すると報告されました。当時愛媛大学小児科にMGの患者さんが入院していました。その患者さんのAChR抗体をぜひ測定したいと考え、発表されたばかりのLindstromの論文を参考にAChR抗体の測定方法を確立しました。当時抗体を測定できる仕組みがわが国にはなかったために、全国から患者血清を送っていただき、抗体価を測定しました。MGの病態は神経筋接合部の形態崩壊を主体とした情報伝達異常が本体で、その崩壊機序に免疫学的な攻撃が大きな役割を演じていること、補体が神経筋接合部の崩壊を促進することなどのMGの病態は多くが1970年代に明らかにされました。
(イ)Seronegative MG
AChR抗体の測定はその後ルーチン化され、一般病院の普通の検査として活用される時代になりました。その結果、抗体価が認められない“Seronegative MG”の患者さんが20%ほど存在していることが明らかになりました。MGという疾患は、抗体が原因で神経筋接合部での情報伝達を障害するものと理解されています。ではSeronegativeとはどういうことなのでしょうか。世界中でその研究が進められています。Seronegative MGとは、もともとAChR抗体が陰性のことを言っていましたが、後述するように、その考え方が変化してきています。
MGは大きく眼筋型と全身型に分類できます。小児では眼筋型が多く60%を占め、眼筋型はAChR抗体価も低値で、陰性の比率も高いことが知られています。眼筋型の多い小児MGではSeronegative MGが多いのです。本当に抗体が存在しないのか否かは大きな課題ですが、その研究の中で、Musk抗体が実際にMGを引き起こしていることがOxfordのグループによって明らかにされました。Muskという蛋白質は神経筋接合部に存在し、AChRが神経筋接合部に集合するために必須の物質です。Muskが欠損している病態やMuskの本来の機能を抗体が阻害することで、AChRが群形成できず、神経からの情報伝達が効率よくできなくなり、MG病態を発症するものです。Musk抗体陽性の小児例の報告は散見されます。その後Musk以外にもLrp4抗体がMGを引き起こすことが明らかとなりました。Lrp4もMuskと一緒になってAChRの群形成に大きくかかわる物質です。この抗体が存在することによってMuskとLrp4の複合体形成ができなくなり、ひいてはAChRの群形成を阻害します(図2)。
AChRの群形成に関わる蛋白は、これ以外にも数多く存在し、その蛋白に対する抗体も幾つかに認められています。それらの抗体が本当に発症にかかわっているか否かの検証はこれからの問題です。このように、Seronegative MGという言葉の意味もここ10年で大きく変わってきています。

(図2)
(ウ)先天性筋無力症候群
小児期でもう一つ問題となるのは先天性筋無力症候群という病態です。これは神経筋接合部の様々な蛋白質に異常がある場合、そこでの情報伝達が障害されることによって起こる病態で、その原因はそれぞれの蛋白質をコードしている遺伝子の異常と考えられています。この蛋白質の多くは、前述のAChRの群形成に関わるもので、こういった蛋白質の持つ機能が抗体で阻害されるという病態がSeronegative MGの研究の中で確立しつつありますが、先天性筋無力症候群とは遺伝子異常で十分な機能を発揮できる蛋白が存在しない病態と考えられます。つまり、前述のSeronegative MGと先天性筋無力症候群の考え方がかなり近いものになってきたと感じています。
胸腺について
胸腺という臓器は前胸部の中央を上下に走る胸骨の裏に存在し、免疫の発達に大きな役割を果たしています。ヒトは生まれながらに全員持っているのが当たり前の臓器で、もし存在しなければ、原発性免疫不全になってしまいます。血液に含まれる細胞成分は原則骨髄で作られ、成熟して十分機能する状態に成長して初めて末梢血中に出てきます。
しかし、一部のリンパ球はその状態でも不十分で、胸腺という臓器に取り込まれ、そこで自己と非自己を区別できるように教育されて、再び末梢血に出てきます。これは免疫の持つ本来の機能です。免疫とは、細菌やウイルスなどヒトの体に害を及ぼす病原体が体内に入ってきたときに、それを敵とみなして攻撃し排除する機能です。その相手が敵なのか味方なのかをどうやって見極めているのかは、長い間大きな謎でした。それが明らかにされたのは1990年ころの大きな出来事でした。その結果明らかになったことは、骨髄から末梢血に出てきたT細胞リンパ球は胸腺に取り込まれ、その中をめぐる間に様々な体内に存在する蛋白質と出会い、その結果自己と非自己を識別する機能を持つまでに十分教育受けるということです。それが不十分な場合には、間違って自己を非自己と認識し攻撃してしまう、いわゆる自己免疫疾患を起こしてしまうことになります。このように本来胸腺とは免疫の発達には重要な臓器です。子供たちが保育園や幼稚園に通う幼い時期に様々な病原微生物に出くわし、その都度発熱したり下痢したりを繰り返す、その一つ一つのエピソードが、新しく免疫の力をつけていっていることを意味します。
胸腺は若い年代で免疫の確立に一仕事を終えた後は委縮してしまい、多くは20~30歳くらいではなくなってしまうことが普通です。成人に多く発症する胸腺腫はまた別の意味合いを持ちます。本来委縮すべき胸腺が反対に腫大化して、腫瘍として人に害を及ぼしているわけですから、摘除するのは本来の治療と考えられます。小児期の胸腺腫大は、生理的なレベルが多く、異常としても過形成のことがほとんどですから、これを摘出するか否かは慎重に判断しなければなりません。摘出する場合でも現在の考え方は、米国のガイドラインから見ても、思春期後(10歳以後)を考えたいと思います。
家族歴がある場合
MGが家族や親戚におられる場合、遺伝がどうかという問題はご心配の点だろうと思います。家族内発症についての論文はいくつか出ていますが、凡そ5%位といわれています。私の患者さんでの頻度からしてもほぼそのくらいかと考えます。むしろ問題は、MGの病態は前述のとおり自己免疫疾患で、自己のはずの構造を異物と間違えて認識してしまうという病態が体の中に存在するということです。つまり、甲状腺疾患とかSLEとか関節リウマチなどのほかの自己免疫疾患をご家族の誰かが持っている場合には、MGも出てきやすいと思います。
MGを持つ母親から生まれた赤ちゃん
AChR抗体陽性の母親から生まれた赤ちゃんは全員MGを発症するのでしょうか。答えは「NO」です。抗体は胎盤を経由して胎児にも移行します。したがって母親の抗体価が高ければ当然胎児にも抗体は移行し、症状が出現するはずです。ところが、MGを発症する赤ちゃんは12%くらいといわれ、新生児一過性筋無力症といわれています。これが何故かは実はよく解っておりません。
母親のMG症状も妊娠によって変化し、妊娠後期から出産後暫くは症状が改善・緩和し、その後症状が悪化することが見られます。生まれた赤ちゃんも生直後に症状は出てこず、数日して症状が発現してきます。これは、妊娠中のホルモンの変化によると考えられており、特に妊娠末期~分娩の時期は生理的ステロイドホルモンが大量に分泌されているために症状は改善します。分娩前後はアルファフェトプロテインという物質が急激に増加し、その後消退することも影響していると考えられています。
この新生児一過性筋無力症は、自分で産生する抗体によるものではなく、母親の抗体が経胎盤的に移行したものなので、時間とともに低下していきます。生後数日で症状が出たとしても、数週間症状が続く間の治療・管理を続けると、次第に治まっていきます。稀に母体の抗体が特殊で、高濃度に胎児に移行し、胎内での動きを抑えるくらいに強い影響を与える場合には、その胎児は先天性関節拘縮という病態を発症することがあります。
MGの診断
(ア)症状
MGの病態は神経筋接合部での情報伝達障害で起こります。したがって筋力低下や易疲労性が主体になります。日内変動があり、休息により症状が改善するのが特徴です。朝は元気だったのに、午後になると横になることが多く、そのために仕事をするうえで誤解されやすい、周りにわかってもらえないという悩みを抱えることがよくあります。MGという病気を持っていても、周りの理解があれば、十分に活躍できる場面が数多くあると思います。そのためには、周りの人に病気のことを伝え、理解していただくことも重要ではないかと感じています。
MGには大きく分けて眼筋型と全身型があります。瀬川昌也先生と野村芳子先生はこれに潜在性全身型の概念を追加されました。MGの病態が自己抗体で起こると考えられている以上、眼筋にしか症状がない場合でも全身の他の筋肉にも抗体が沈着し、発症の閾値の問題で発症に至っていない病態というのが潜在性全身型の考え方です。眼筋型と判断されていた患者さんの筋電図を検査することでWaning現象を確認して潜在性全身型と診断する場合はよくあります。これによって治療法が大きく変わってきます。
眼筋型が小児では多く、成人でも多くは眼筋症状で発症し、後に全身型に移行することが多いです。何故眼筋型が多く、眼筋が障害されやすいのでしょうか。四肢筋の神経筋接合部と眼筋のそれとを比較すると、形態的に眼筋の神経筋接合部の方が複雑な形態をとっていること、電気生理学的に幾つかの違いがあり、眼筋には眼球の迅速な動きを求められていること、さらにAChRのサブユニットが異なり、本来α、β、ε、δの4種類からなる四肢筋AChRに対して、眼筋のAChRサブユニットはεがγに置き換わっていることが知られています(図3)。こういった神経筋接合部の相違によって、眼球の細かな複雑な動きに対応しているわけですが、絶対的な筋肉の大きさ・太さの差が、いわゆる“Safety factor“と呼ばれる安全域〈余裕〉の差を生みだしており、余裕のない眼筋に症状が出やすいと説明されています。

(図3)
(イ)テンシロンテスト
短時間作用型の抗コリンエステラーゼ剤であるアンチレックス〈テンシロン®〉を静脈内投与し、1分から3分の間に起こる症状の変化を確認します。病態によっては必要とされる投与量が微妙に異なる場合がありますから、患者さんによって工夫が必要です。重症の場合はアンチレックス2mgでは全く効かない場合がありますし、4mgでは多すぎる場合もあります。またMusk陽性MGではアンチレックス投与で症状がむしろ悪化する場合もあり、要注意です。
(ウ)誘発筋電図
多くは前腕の神経を刺激してその支配領域の筋肉を使い電位を確認する方法で、初回の刺激で起こる電位に対して、5発目の電位がどのくらい小さくなっているかで陽性か否かを判断します。眼筋型を検査する場合は、眼筋は瞬きで電位がうまく取れないため、鼻筋を用います。潜在性全身型を判断する場合には重要な検査となります。神経刺激はかなり痛みを伴うため、あまり頻繁に行いたくはない検査ですが、必須の場合があります。
治療
(ア)抗コリンエステラーゼ剤
筋肉に神経からの情報を伝達するためには、神経末端からアセチルコリンを分泌し、それが反対側の後シナプス膜まで拡散していって、後シナプス膜にあるAChRと結合して受容体の中央を貫通するチャンネルを開放します(図4)。きわめて短時間解放されたイオンチャンネルを後シナプス膜内外のイオンであるNaとKがそれぞれ流入、流出して、その結果後シナプス膜の電位変化を起こします。これが一定以上の変化をきたしたときに筋肉収縮が起こるわけです。神経から筋肉にうまく情報が伝達するためには、この構造が形態的にしっかり構築され、かつ一つ一つの蛋白質の機能が十分働くことが必要です。
コリンエステラーゼは、神経筋接合部で神経末端から放出されるアセチルコリンが、反対側の後シナプス膜にあるAChRと反応して、神経末端からの情報を伝達した後アセチルコリンを分解するために働く酵素です(図4)。 こうして分解されたアセチルコリンは再び神経末端に運ばれ、アセチルコリンを再合成して、無駄のない効率的な情報伝達を行っています。即ち、抗コリンエステラーゼ剤を使うことにより、アセチルコリンの分解を抑えて、相対的に多量のアセチルコリンが存在する状態を神経筋接合部に作り出すことになります。MGの病態が神経筋接合部の機能異常による情報伝達障害ですので、効率の悪い情報伝達を何とか機能させたいと、抗コリンエステラーゼ剤を投与します。つまり、多くの場合少なくなったAChRを無理にでも働かせて情報の伝達を進めようという治療法なのです。従ってこの使い方が不適切な場合には、コリナージッククリーゼを引き起こして、急激な症状の悪化を招きます。
この系統の薬は作用時間の違いによって使い分けます。短時間作用型のアンチレクスは、数分しか作用しませんから治療薬というよりは検査薬として活用されています。よく使われるメスチノン®やマイテラーゼ®はそれぞれ4~5時間及び5~8時間ほど作用し、ウブレチド®はさらに長時間作用型です。この作用時間を把握したうえで投与・服用していただく必要があります。患者さんの生活パターンから服用時間を微妙に工夫することも可能です。抗コリンエステラーゼ剤は、上記の理由でできる限り短期間の使用にとどめたい薬ではありますが、場合によってはそれを長期間続けなければならない状況もあり得ます。その場合はできる限りで少量にとどめることが必要です。

(図4)
(イ)ステロイド
ステロイドは1950年代に世に出てきた薬で、現在でもまだ謎が多いけれども非常に有効な、魔法のような薬です。従って、いくつかの免疫抑制剤を使うことができるようになった現在でも、MG治療の中心として位置付けられています。
ステロイドを投与する場合は、適応基準として、全身型で相応の重症度があることが求められます。ただし、Seronegative MGでも使う場合がありますし、眼筋型でも使う場合は頻繁にあります。それぞれの患者さんの病態をしっかり見極めての投与が求められます。
投与開始後の1週間から10日間くらいの間は、初期増悪とよばれ、MG症状が一時的に悪化する時期があります。従ってステロイドを開始する場合には入院して治療を開始することが多いと思います。また、初期増悪が高じて全身状態の悪化が予想される場合には、事前に初期増悪症状を抑えるための治療を行ったうえでステロイド治療を行う場合があります。例えばAChR抗体価が非常に高い場合には、筋無力症クリーゼと呼ばれる重篤な病態に陥ることがありますから、事前に血漿交換やカラム吸着で抗体価を十分落としたうえでステロイドを開始します。
この初期増悪の出現をできる限り防ぐために、ステロイドは比較的少量から開始して、初期増悪の様子を見ながら漸増していきます。最大投与量に到達したら、その量でしばらく続けてMG症状を抑え込みます。寛解を確認して数か月その量の投与を持続した後で、ゆっくりと漸減していきます。成人領域ではこの期間をできる限り短縮したいと、免疫抑制剤を積極的に使う方向で動いているようですが、小児科領域でもその方向性は正しいと思います。成人領域でのステロイドの使い方は、投与量が多い場合心理的な抑うつ状態を作りやすいために、できる限り早めに5㎎/日以下の投与量に減量するというものです。うつ傾向という病態は小児ではあまり見かけないことかもしれませんが、ステロイドの持つ作用機転からして起こりうるものです。今後小児科領域でも注意してみていく必要があります。
小児科領域で特徴的な大きな問題は「成長」です。ステロイドは脳下垂体からの成長ホルモン分泌を抑え、成長を障害します。小学校高学年から高校生の成長期の子供たちに大量のステロイドを長期間使うことは、成長(伸長)を阻害し、最終身長を低くしてしまい、患者さんのその後の生活に心理的な負の要因を作ってしまうことになります。身体的な成長がすでに終了した大人との大きな違いです。
そのほかにもステロイドという薬は様々な副作用を持っています。その副作用をできる限り少なくしたいと編み出された投与方法が隔日投与法です。ステロイドはその種類によって(抗コリンエステラーゼ剤と同様に)作用時間が異なります。経口剤として頻用されているプレドニン®(プレドニゾロン)は生物学的半減期が約1日で、2日に1回の投与とすることで、次の服用前のステロイド効果はほとんどなくなってきています。ステロイド効果のなくなる時間を作るということが重要で、その結果副作用をできる限り少なくできるわけです。
このようにステロイドは古くから使われて、多くの患者さんの命を救ってきた魔法のような薬です。が、副作用も多く、慎重に使い続けていかなければなりません。医学の進歩によりステロイドにもいくつかの種類が出てきて使い分けが可能になり、さらに次に述べる免疫抑制剤の開発によって、難治のMGを比較的容易に治療ができる時代になってきました。
(ウ)免疫抑制剤
免疫抑制剤は、免疫の調節にかかわる薬剤のことで、ステロイドも広い意味ではこれに含まれます。免疫は、前述のように、自己と非自己を識別して非自己だけを攻撃・排除する身体の仕組みです。ウイルスが体内に侵入してきた場合、ウイルスを攻撃するために免疫を活性化させる方向に免疫のバランスをシフトさせ、細菌が侵入してきたら細菌を攻撃する方向にシフトさせます。細菌を攻撃するのは白血球の中でも主に好中球で、ウイルスを攻撃するのは主にリンパ球です。リンパ球にもT細胞やB細胞などがあり、それぞれが様々な物質を分泌して自分を活性化させたり増殖させたりして、免疫に関わっています。
免疫抑制剤は、それぞれ薬によってどの機転で作用するかが異なり、本来はそれをうまく調節するように投与方法を考えたいところです。現在保険適応のあるタクロリムス(プログラフ®)およびサイクロスポリン(ネオーラル®)はともにカルシニューリン阻害剤と呼ばれる種類の薬で、作用機転はT細胞の活性抑制です。MGは自己抗体によって惹起される病態と考えられていますので、その意味では抗体産生に大きくかかわるB細胞を抑制する力を持つミゾリビン(ブレデニン®)やミコフェノール酸モフェチル(MMF、セルセプト®)、サイクロフォスファマイド(エンドキサン®)なども十分検討すべき薬と思います。
タクロリムスは胸腺摘出後にのみ使うことができるという保険適応の縛りが取れ、必要な患者さんではしっかり使える状況になりました。ステロイドの副作用をできる限り抑えるために、タクロリムスなどの免疫抑制剤をうまく使っていきたいと思います。こういった薬はまだ投与され始めて歴史が浅いものですから、長期間投与することの弊害などは十分わかっているとは言えません。それでも現在多くの患者さんで投与されており、その効果についての知見が集積して行きつつあります。
前述のように長くステロイドによる治療方法しか選択肢のない時代がありました。が、現在は複数の免疫抑制剤が投与可能となりました。それでもなお、現在保険適応で使うことのできる免疫抑制剤は限られており、タクロリムスとサイクロスポリンしかありません。それ以外の有望な免疫抑制剤についても保険適応が取れるように働きかけていきたいものです。
(エ)胸腺摘出術
胸腺は前述したように免疫を司る重要な臓器です。成人でその役割を終えた段階での摘出は、手術自体や麻酔の合併症などの問題を除けば、むしろ合理的な方法かもしれません。若い女性での拡大胸腺摘出術は、前胸部に大きな手術痕を残すために、美容的に大きな問題でした。これも最近は内視鏡的手術が一般的になってきており、選択しやすい状況が生まれています。胸腺摘出術は自らの身体にメスを入れるのですから、その選択は大きな決断に違いはありません。ステロイドや免疫抑制剤などの内服薬で効果が十分でないと判断され、さらなる改善を希望する場合に初めて選択されるべきものと思います。
手術を実施した場合に、手術の侵襲によるものと考えられますが、一時的にMG症状が悪化することがよくあります。これが数週間に及び、完全に安定化するのに半年くらいかかる場合もあります。ステロイドの初期増悪への対応と同様に、手術によって状態悪化が予想される場合には、手術前に血漿交換やカラム吸着などによって全身状態を安定化させて手術を実施する、という方法をとる場合があります。
胸腺摘出術を施行するか否かの適応に関して、小児の場合は成人での判断と大きく異なります。これは、免疫の確立がまだ不十分な時期での胸腺摘出が果たして適切かどうかの議論にまだ決着がついていないからです。一方で、胸腺摘出をする場合、MGの発症から手術までの期間ができる限り短期間のほうが効果が大きいということも知られています。幼くして発症した場合に胸腺摘出を選択したいと考えた時、思春期以後まで待てないという状況も起こり得るため、難しい問題が残ります。
(オ)血漿交換・カラム吸着
血漿交換やカラム吸着は、MG患者さんの血清中に何か症状を惹起する物質が含まれており、それを除去することで症状の改善を図るための方策です。除去されるものはAChR抗体やMusk抗体などの自己抗体、あるいはリンパ球などが分泌するサイトカイン・ケモカインと呼ばれる活性物質などです。これを一時的に除去することで症状を改善するわけですが、このままであれば1か月もすれば抗体価も元の数値に回復しますし、症状も元通りとなってしまいます。従って、この除去方法を選択する場合は、同時に免疫療法なり胸腺摘出なりの根本的な治療を合わせて行うことが必須です。
血漿交換・カラム吸着は、大きな静脈にカテーテルを挿入・維持し、そのカテーテルを使って血液を体外に取り出して有害物質を除去する方法です。除去には、血液を細胞成分と血漿成分に分け、血漿成分を新しい血漿に置き換えて再び体内に戻す血漿交換と、より分けた血漿成分をカラムを素通りさせて、その間に有害物質を吸着しきれいになった患者自身の血漿を体内に戻すカラム吸着があります。1回血漿交換・カラム吸着すると、血小板減少や凝固因子の低下などの副作用が出現するため、その不足を補う治療を追加したり、追加しないまでも回復するのに時間を要するために、1週間に3回くらいまでが限界でしょう。従って入院していただいたうえで2~3週間かけて行う治療法です。
前述のとおり、根本的治療を行う場合に症状の急激な悪化を防ぐためや、現在の重症の状態を一時的に防いで根本治療の効果が出現するまでの時間を稼ぐという目的でこの治療は実施されます。
(カ)ガンマグロブリン治療
ガンマグロブリン大量療法が実施できるようになりました。この治療方法は血漿交換やカラム吸着と同等の効果が得られると考えられており、普通の点滴で行え、カテーテルを長期間挿入しっぱなしという侵襲やリスクがないという点では、大きな選択肢と考えます。小児科領域では、川崎病や血小板減少性紫斑病などでガンマグロブリン大量療法は多数の症例を経験するため、比較的採用しやすい治療法で、1日数時間の点滴を5日間続ける治療法です。副作用はアレルギー反応などに気を付ける必要がありますが、最近の血漿分画成分精製法の進歩の結果、ウイルスなどの混在はほぼ安心できる状況になっており、血漿交換で血漿をそのまま輸注するよりも安全な治療法といえます。
(キ)免疫学的生物製剤
免疫学的生物製剤が大きく進歩しています。膠原病を中心とした自己免疫疾患の治療法として、免疫応答や免疫細胞内の反応を標的としたいくつかの免疫学的生物製剤が開発されてきています。その一部はMGの領域でも試されており、一部は希少疾病用医薬品指定を承認されるところまでに至っております。
それはエクリズマブ(ソリリス®)という薬で、補体のC5という活性物質に対する抗体で、それ以降の反応を抑えようとするものです。MGという病態が神経筋接合部での情報伝達障害で、その機序は免疫応答がうまく調節できずに神経筋接合部の形態まで崩壊させてしまいます。この形態異常を呈するまでにいたるところに補体が関与していることが知られています。ソリリス®を投与することでこの変化を抑制しようとする治療法です。
他にリツキシマブ(リツキサン®)という薬も有効であるとの報告があります。リツキサン®はCD20というB細胞表面にある蛋白質に対する抗体で、この抗体を投与することでB細胞を枯渇させます。B細胞は自己抗体を産生分泌する細胞で、これが枯渇することによってAChR抗体を中心とした自己抗体の産生を抑制しようとするものです。
これ以外にも免疫学的生物製剤が存在し、MGの病態で効果を示す可能性があります。
小児MGについて、その病態、診断、治療の最近の状況をまとめてみました。この半世紀の間にMGの病態は多くの部分が解明され、治療方法も進歩してきました。この間に免疫学が大きく進歩し、難病に指定された当時とは大きな変化です。それでもなお、この病気に悩む患者さんが数多くおられ、解決すべき新たな問題が出てきています。今後さらにこの領域の研究が発展し、さらに病態の解明が進んで、治療法の開発・安全な使用につながっていくことを期待しています。
(市立宇和島病院副院長兼診療部長)